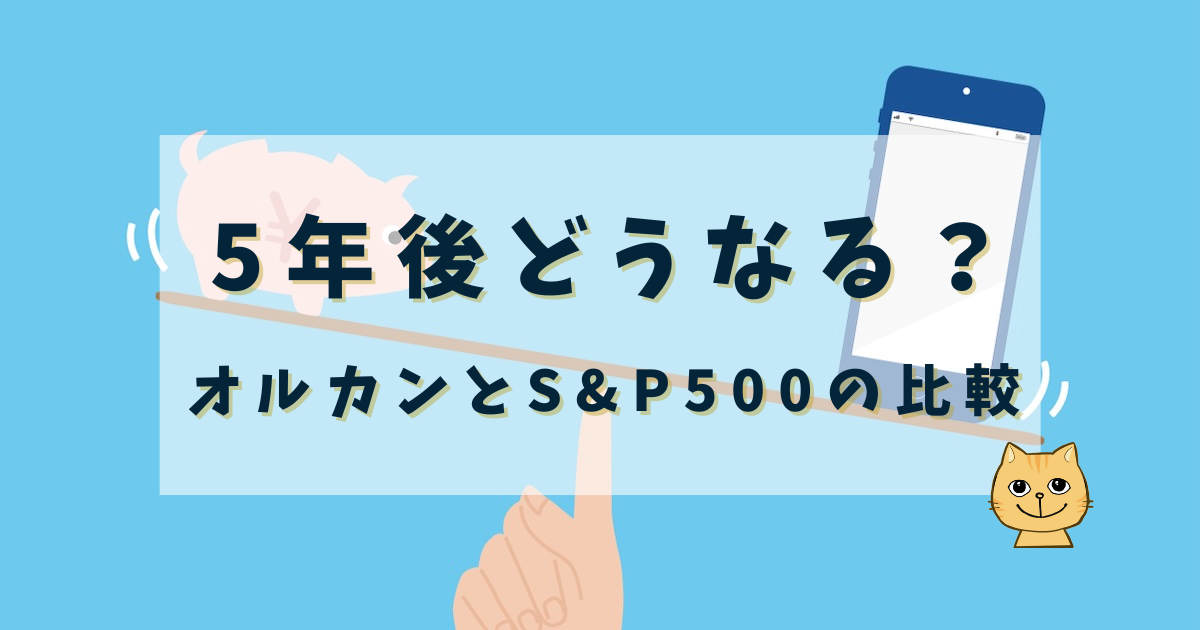オルカンとS&P500、結局どっちを選べばいいのか分からない
そんな悩みを持つ投資初心者の方は多いのではないでしょうか。
オルカン(全世界株式)は分散性の高さと為替ヘッジのないグローバルな成長を、S&P500(米国株式)は経済大国アメリカへの集中投資という強みを持っています。
一見どちらも魅力的に見えるため、迷ってしまうのは当然です。
ですが、「5年後にどんな成果が期待できるか?」という視点で比べてみると、選び方に違いが見えてきます。
この記事では、オルカンとS&P500の違いを、過去データ・リスク・為替・将来性といった切り口で整理し、最終的にどちらが自分に合っているのかを判断できるようサポートします。
記事を読み終えるころには、自信を持って投資先を選べるようになるはずです。
オルカンとS&P500の基本をおさらい
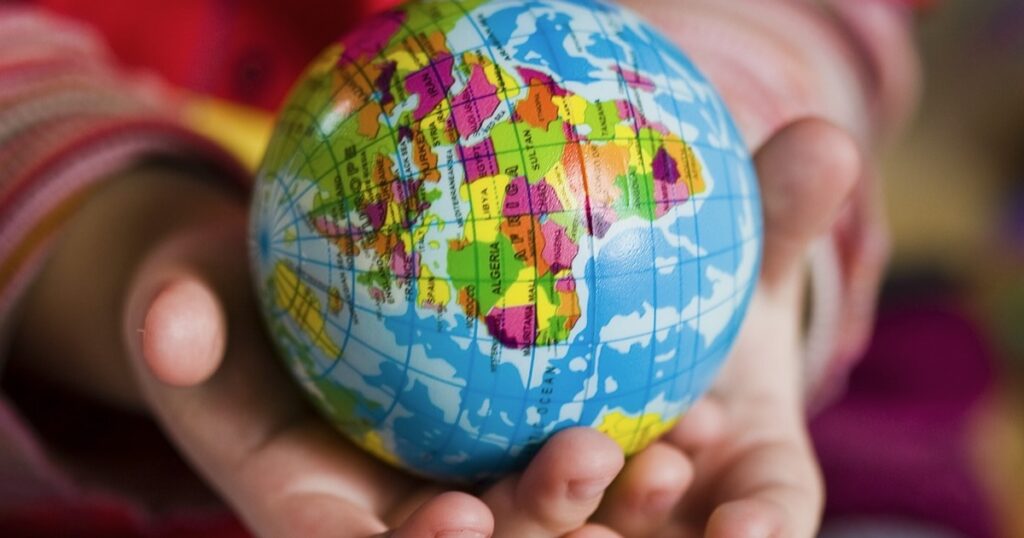

オルカン(全世界株式)とS&P500(米国株式)は、どちらも人気のインデックス投資先ですが、投資対象の範囲とリスク分散のアプローチが大きく異なります。
両者の違いは、主に以下の3点です:
- 投資対象の地域範囲
- 分散性(リスクの取り方)
- 通貨や経済依存度の違い
これらを正しく理解しておかないと、資産配分やリスク管理で判断を誤ることになりかねません。
以下の比較表で、主要な違いを整理してみましょう。
| 項目 | オルカン(全世界株式) | S&P500(米国株式) |
|---|---|---|
| 投資地域 | 日本を含む全世界(先進国+新興国) | 米国のみ(先進国の一国) |
| 主な指数 | MSCI ACWI(オール・カントリー) | S&P500指数 |
| 地域分散 | ◎ 地球規模の分散 | △ 米国一本に集中 |
| 業種分散 | ◎ 世界中の業種を網羅 | ○ 米国内だが業種は幅広い |
| 通貨の影響 | 複数通貨(為替リスク分散) | 米ドル(米国の為替影響を受ける) |
| リスク特性 | 世界経済に合わせて緩やかに成長 | 米国の好調時には高リターンも期待 |
| 経費率(例) | 約0.1133%(eMAXIS Slim 全世界株式) | 約0.0938%(eMAXIS Slim 米国株式) |
- 世界全体にバランスよく投資したいなら「オルカン」
- 米国の成長性を信じるなら「S&P500」
このように、どちらを選ぶかは「リスクをどこまで許容するか」「どの地域の成長に期待するか」によって変わってきます。
次のパートでは、それぞれの過去パフォーマンスを見ながら、さらに理解を深めていきましょう。
資産形成を始めたばかりの方にとって、「オルカン」と「S&P500」の違いは気になるテーマです。
特に【つみたてNISA】や【クレカ積立】を検討している方は、どちらを軸にするか迷うこともあるでしょう。
「つみたて vs 一括」の考え方については、「【投資初心者】一括投資とつみたて投資どっちがいい? 」も参考になります。
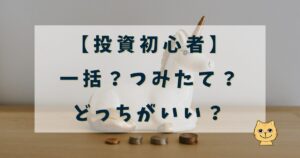
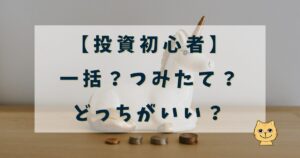
5年間のリターン比較【データ検証】


直近5年間のリターン実績を見ると、S&P500(米国株式)の方が高リターンでした。
しかし、それが今後も続くとは限らないため、数値の背景も含めて冷静に見極めることが重要です。
2020年以降の世界経済は、コロナ禍・金利上昇・地政学リスクなど大きな揺れがありました。
特に米国ではハイテク株が牽引したことで、S&P500が他地域をアウトパフォームしています。
以下は、2020年1月〜2025年4月末までの主要インデックス投資信託の騰落率の比較です(※月末基準、配当込み・税引前)。
| ファンド名(例) | 基準価額(2020年1月) | 基準価額(2025年4月) | 騰落率(約) |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | 10,000円 | 約17,600円 | 約+76% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 10,000円 | 約19,700円 | 約+97% |
※データ出典:三菱UFJアセットマネジメント、各ファンド運用報告書より。数値はおおよその目安。
- 米国(S&P500)は圧倒的な成長を示した
- オルカンも堅調だが、新興国や日本が足を引っ張る場面もあった
- 通貨の為替差もリターンに影響している
- 過去5年ではS&P500がリードしているが、今後の成長性は不確実
- 過去実績=未来保証ではない
- 長期投資では分散性も重要な判断材料
なお、これから「オルカン」や「S&P500」へ投資を始めるなら、NISA対応の証券口座を用意しておくのがベストです。
SBI証券でクレカ積立を設定するだけでもスタート可能です。
投資タイミングと為替の影響


S&P500は「投資タイミング」と「為替」の影響を大きく受けやすい商品です。
リターンに差が出る主な要因は、株価だけでなく「円高・円安」も大きく関係します。
- 米国株は「ドル建て資産」
- 日本の投資信託は、為替(ドル/円)を円換算した価格で評価される
- 円安のときに買うと不利になることも
- 投資タイミングがズレると、想定よりリターンが低下するリスクもある
2020年と2024年の為替と米国株(S&P500)の例を見てみましょう。
| 時期 | 為替(ドル/円) | S&P500指数(USD) | 円換算後の評価 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月 | 約105円 | 2,200 | 円安メリット小 |
| 2022年10月 | 約150円 | 3,500 | 円安で押し上げ |
| 2024年5月 | 約155円前後 | 5,200 | 為替益が目立つ |
- 同じS&P500でも、為替によって投資成果が大きく変わる
- 長期投資ならブレは吸収できるが、短期ではリスクになる
- 為替は読めないため、一括投資より分散投資が有効
- S&P500はパフォーマンスが魅力でも、「円高→円安」の恩恵を受けた側面がある
- 今後、円高に戻ればリターンが下がるリスクもある
- 投資時期や通貨の影響も考慮して判断を
為替の影響を受けにくくしたいなら、つみたて投資による分散が効果的です。
「新NISA」でのつみたて戦略について詳しく知りたい方は、「投資初心者でも始められる【新NISAクレカ積立】の方法 」をご覧ください。
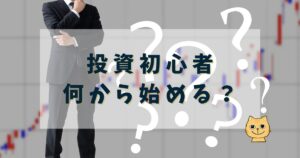
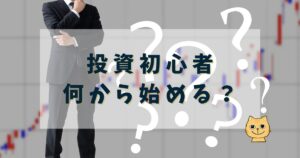
リスク分散と将来予測の考え方


資産運用において「未来を予測する」のは困難だからこそ、リスク分散が重要です。
オルカンとS&P500を比較するうえでも、この視点は避けて通れません。
特定の国や地域だけに投資する「集中投資」は、好調時にはリターンが大きい反面、ひとたび下落すればダメージも大きくなります。
一方、全世界に広く分散する「オルカン(全世界株式)」は、国・地域・通貨・産業セクターをまたいで投資できるため、ある程度の下落リスクを抑える効果が期待できます。
実際、米国株一辺倒だった人が、近年「中国」「ヨーロッパ」「インド」などの成長期待を見直して、全世界投資へ乗り換えるケースも増えています。
| 分散の種類 | オルカン | S&P500 |
|---|---|---|
| 国の分散 | 約50カ国以上 | 米国のみ |
| 通貨の分散 | 円・ドル・ユーロなど複数 | 米ドル |
| セクターの分散 | グローバル全体 | 米国中心の構成 |
例えば、米ドル安が進行した場合、S&P500だけに投資していると為替損失の影響を強く受けます。
一方、オルカンなら他通貨資産も含まれているため、バッファ効果が生まれます。
どちらが正解かは将来にならないとわかりませんが、リスクを減らすなら全世界、リターンを狙うなら米国集中というのが一つの基準です。
もし、長期で安心して積み立てたい方は、「分散性」と「自動積立」のある制度をフル活用しましょう。
新NISAでの分散投資を成功させるコツはこちらです。
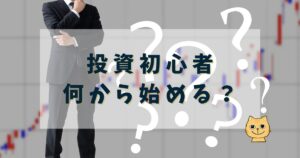
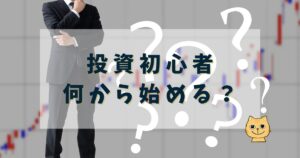
マネーフォワード MEで投資・家計を一元管理もできます。


まとめ|初心者が選ぶべき判断ポイント


最後に、オルカンとS&P500、どちらを選ぶべきか――初心者に向けて判断の軸を整理します。
こんな方にはオルカン
- 世界全体に分散投資して安定したリターンを期待したい
- 米国以外の成長国にも長期的に投資したい
- 通貨分散(為替リスク軽減)を意識している
- リバランスなどを気にせず、1本で完結させたい
初心者に特に人気の投資信託【eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)】は、楽天証券やSBI証券のクレカ積立でも購入可能です。
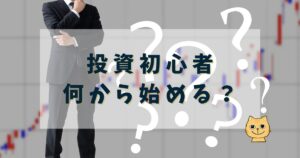
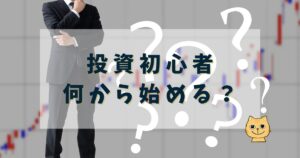
こんな方にはS&P500
- 米国の成長力を信じて集中投資したい
- 近年の高パフォーマンス(ハイテク株)を重視している
- リターンを最大化したい意志がある
- 為替の影響をあまり気にしない(むしろ円安メリットを享受したい)
特に【SBI証券】×【三井住友カード】の組み合わせなら、S&P500投資もポイント還元でさらにお得です。


どちらが正解というより、自分の価値観や投資目的に合っているかが重要です。
迷ったときは「両方に少しずつ投資して、あとで調整する」という方法も有効です。
証券口座をまだ開設していない方は、まずはSBI証券で始めましょう。
すでに口座がある方は、毎月のクレカ積立や自動積立の設定を見直して、コツコツ継続できる環境を整えてください。
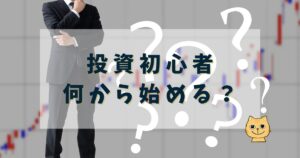
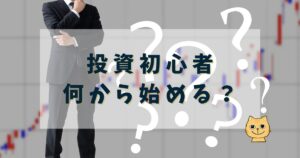
投資の第一歩は「知ること」。
次の一歩は「始めること」。
未来の自分のために、今日から動き出しましょう!