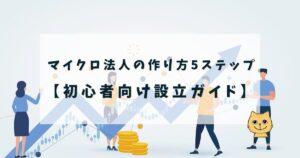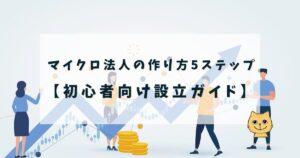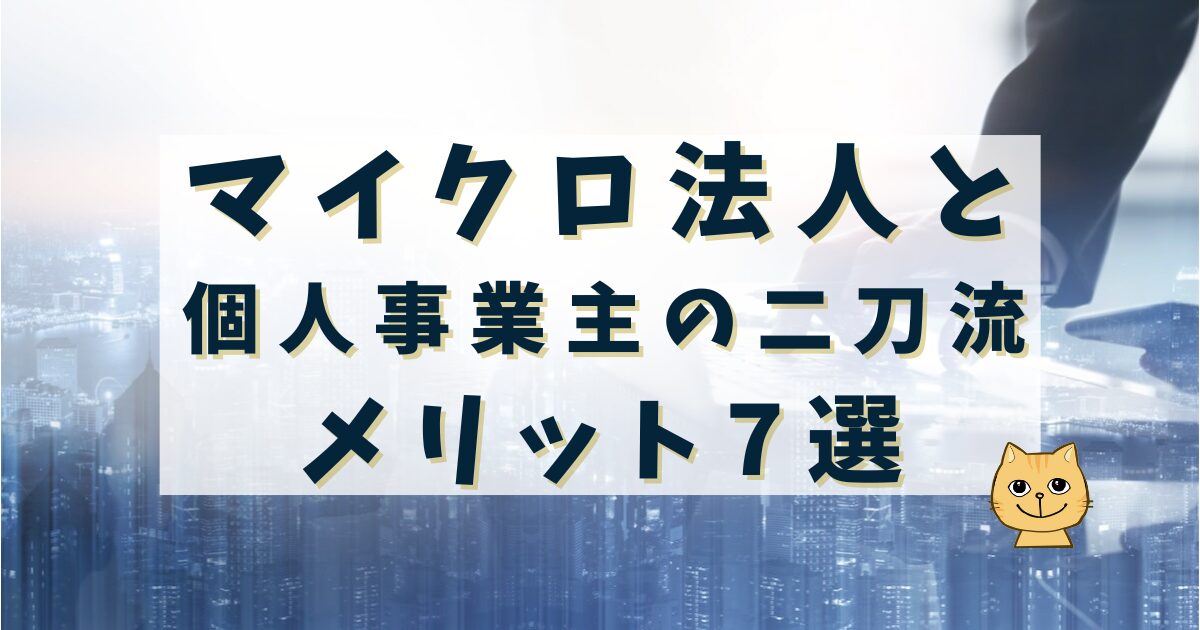節税も保険料の最適化もあきらめない。
マイクロ法人×個人事業主の“二刀流”で得られる7つの実践メリットを解説!
マイクロ法人と個人事業主を両立することで、節税や社会保険料の最適化が現実的に狙えるようになります。

マイクロ法人と個人事業主、両方を運営する意味が本当にあるの?
そう思う方も多いはずです。
「法人化すれば節税になる」と聞いても、実際にどのようなメリットがあるか分からず、個人事業主だけで続けている方も少なくありません。
実はこの“二刀流”戦略によって、社会保険料の調整や所得分散による節税、経費の柔軟な活用、契約や与信の強化など、片方だけでは得られない多面的なメリットが生まれます。
私自身も、インデックス投資で得た資金をもとにマイクロ法人を設立し、個人事業主と併用してサイドFIREを達成しました。
現在はすべての仕事を在宅で行い、会社勤めなしでも安定した収入と自由な時間を両立しています。
本記事では、そうした実体験をベースに、「法人+個人事業主」で得られる実践的なメリットを7つに整理してお届けします。
「少しの準備で、大きな効果を得る」
——そんな併用戦略の全体像を、あなたの選択肢に加えてみませんか?
社会保険料を最適化できる
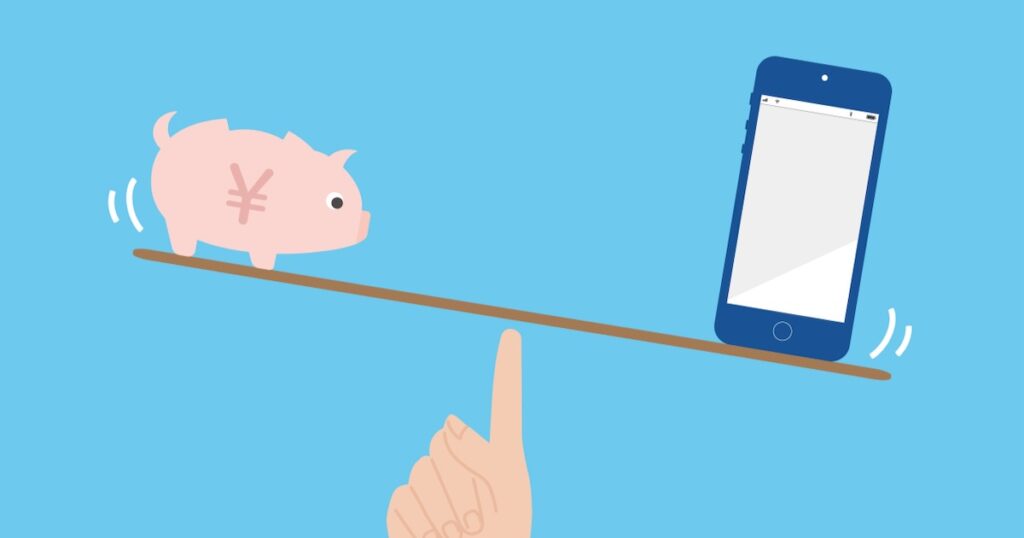

マイクロ法人を活用すれば、社会保険料は「設計するもの」になります。
個人事業主の場合、国保・国民年金への加入は避けられず、所得に応じて保険料が青天井に膨らみます。
一方、法人を設立して役員報酬を設定すれば、厚生年金+協会けんぽ(いわゆる社会保険)に切り替え可能。
報酬額をコントロールすることで、将来の年金額も見込めるうえ、保険料も戦略的に最適化できます。
つまり、「どんな収入で、どう受け取るか?」を自分で決められるのが、マイクロ法人の最大の強みです。
具体例:私の社会保険料の最適化
私の場合、役員報酬は月6万3,000円未満に設定。
その結果、社会保険料は最低等級で協会けんぽ+厚生年金に加入しつつ、将来の年金額も上乗せできる状態に。
また、個人事業主側の所得を抑えているため、国保・国民年金には一切加入せず、保険料ゼロを実現しています。
比較表:個人事業主 vs マイクロ法人(社会保険)
| 項目 | 個人事業主(国保+国民年金) | マイクロ法人(協会けんぽ+厚生年金) |
|---|---|---|
| 加入義務 | 必須 | 報酬ありで切り替え |
| 保険料 | 所得に比例(青天井) | 定額制(等級に応じて) |
| 控除 | 国民年金等控除 | 社会保険料控除(年金額も上乗せ) |
| FIRE向き? | ✕ | ◎ 調整・設計しやすい |
法人設立後の手続きはこちらの記事も参考になります:
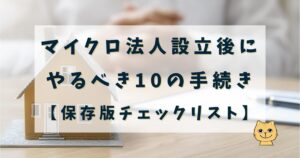
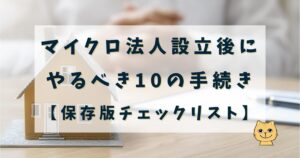
所得分散による節税ができる


マイクロ法人と個人事業主を併用すれば、「2つの財布」を使って税負担をコントロールできます。
ポイントは、収入を法人と個人に分けること。
それぞれの税率や制度を活かして、トータルの税負担を最適化することが可能です。
個人の所得が増えると負担が重くなる
- 個人の所得が増えると、所得税+住民税の累進課税で急激に負担が重くなる
- 一方、法人の税率は実効税率 約23.2%で一定
一定の利益までなら法人の方が有利 - 2つの所得に「振り分けられる」ことで、どちらか一方に極端な税負担がかかるのを防げる
つまり、「バランスよく受け取る」だけで、賢く節税できる仕組みなのです。
具体例:私の所得分散
| 区分 | 所得の扱い |
|---|---|
| 法人 | Web制作・不動産賃貸 → 法人で受け取る |
| 個人 | 土地の賃貸 → 個人事業で計上 |
このように、業務内容や収入源に応じて役割を分担することで、ムリなく所得分散が実現できます。
モデルパターン別の比較
| 年間所得 | 法人併用なし | 法人+個人併用 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 所得税・住民税が重い | 法人を使って定率で抑える |
| 300万円 | 最低税率でも社会保険が重い | 法人報酬で最適水準に設計 |
法人と個人を使い分ける設計力が、節税のカギ。
この分散戦略は、記事「マイクロ法人で二刀流!FIREを実現する7つの方法」でも詳しく紹介しています。
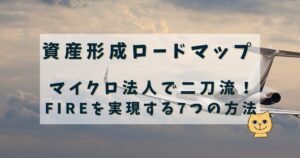
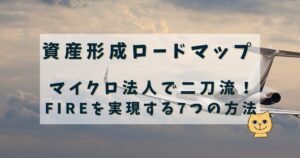
経費計上の幅が広がる


法人と個人の“二刀流”にすることで、経費の取り扱いに柔軟性が生まれ、節税の選択肢が一気に広がります。
マイクロ法人と個人事業主を併用すると、それぞれの事業に適した経費を計上できるため、無理なく合法的な節税が可能になります。
特に、経費として計上できる内容は業種や契約形態によって変わるため、法人と個人という2つの視点を持つことで「どちらで計上すべきか」を柔軟に選べるのが大きなメリットです。
たとえば、同じ「通信費」や「家賃」であっても、
- 法人として契約すれば法人経費
- 個人の事業で使えば個人経費
と、使い方に応じた計上が可能になります。
具体例:私の経費計上
- 法人では、Web制作・ブログ運営に関するPCやモニター、ドメイン代などを計上
- 個人では、土地の賃貸に関する固定資産税や修繕費などを計上
それぞれに必要性と合理性のある支出を経費に分けて計上しています。
経費を分けることで得られるメリット
- 必要経費の範囲が拡大:法人と個人それぞれで認められる支出が違うため、節税余地が増える
- 税務リスクの回避:1つの事業で無理に経費を通すよりも、実態に合わせた適切な按分が可能
注意点:二重計上はNG
経費の計上は、1つの支出を両方で計上することはできません。
法人か個人、どちらか一方で正しく処理することが重要です。
経費設計の考え方は、こちらでも詳しく解説しています。


クラウドサービスで会計・申告も簡単に管理できる


マイクロ法人と個人事業主の“二刀流”でも、クラウド会計ソフトを使えば、会計と申告の手間を最小限に抑えることができます。
一見すると「2系統の会計管理は面倒そう」と感じるかもしれませんが、役割を分けてソフトを使い分けるだけで、仕訳や申告の作業はかなりラクになります。
クラウド型ならインターフェースも直感的で、経理初心者でも操作しやすいのが大きな魅力です。
具体例:私のクラウド会計ソフト運用
| 区分 | 利用ソフト | 主な用途 |
|---|---|---|
| マイクロ法人 | マネーフォワード クラウド会計 | 月次の会計入力、決算書作成、税務申告書の作成補助など |
| 個人事業主 | マネーフォワード クラウド確定申告 | 青色申告書の作成、経費計上、収支管理 |
どちらも銀行口座やクレカと連携しているため、仕訳の自動化が進みます。
また、帳簿の形式も電子帳簿保存法やインボイス制度に完全対応済みで、法人・個人ともに安心です。
在宅ワークでも会計は“二刀流”で一元管理
実際に私も、クラウド会計ソフトのおかげで法人・個人の経理を1つの感覚で同時に管理できています。
- 会計初心者でも安心して導入できる設計
- 初期費用ゼロから無料体験でスタート可能
- 節税と業務効率化の両立が可能
法人と個人、それぞれに最適なクラウド会計ソフトを導入することで、FIRE後の経理も手間なく継続できています。
クラウド会計や税務サービスの活用例をさらに詳しく紹介しています。


私も実際に使っているクラウド会計ソフトで、会計初心者でも安心して使える設計になっています。
導入がまだの方は、まずは無料体験から試してみてください。
マイクロ法人の会計で節税と業務効率化を両立させる最強ツールです。
個人事業主で手間なく・ミスなく・青色申告を最大限活用できます。
在宅ワークでも法人の信用を活かせる


在宅でも法人を設立することで、対外的な信用力を活かした活動が可能になります。
「法人契約ができる」「法人口座を持てる」といった信用の土台があるだけで、在宅ワークであっても事業運営の幅は大きく広がります。
たとえば個人名義での契約や取引は、相手によっては「責任の所在が曖昧」と見なされ、信頼性が劣るケースがあります。
しかし、法人を設立しておけば、契約・請求・口座運用などすべてを「法人名義」で行えるため、対外的な印象も大きく変わります。
これは在宅ワークで事業を行う方にとって、非常に大きなアドバンテージです。
実体験:私の在宅ワークでのマイクロ法人設立メリット
- 法人口座(住信SBIネット銀行)を開設し、業務資金と私的資金を完全に分離管理
- 請求書や契約書も法人名義で統一
- 法人名のドメイン・メールアドレスを取得し、信頼性を補強
- 税務署・金融機関・取引先からの評価も良好に
こうした仕組みのおかげで、私は「在宅でも法人として存在している」ことを前提に、安定した取引と信頼を築いています。
いまや「オフィスがあるかどうか」よりも、「きちんと法人格があるか」が評価軸になる時代です。
たとえば私の場合も、請求書に記載された法人名・法人メール・銀行口座名義によって、相手先からの印象がまるで違いました。
在宅でWeb制作や物販、ブログ運営などを行う方にこそ、「信用の土台」としての法人化は強くおすすめできます。
法人口座の開設方法はこちらで詳しく紹介しています。


住信SBIネット銀行は、オンライン完結で開設でき、マイクロ法人に人気の高いネット銀行です。
- すべての手続きがネット完結
- 書類作成の丁寧なサポートあり
将来の出口戦略に柔軟性がある


マイクロ法人と個人事業主の二刀流にすると、将来のライフスタイルに応じて柔軟な出口戦略が選べます。
これはFIRE後の選択肢として非常に重要です。
法人と個人、2つの収入軸を持っていることで、「どちらかを続ける」「どちらかを縮小・終了する」などの選択ができるようになります。
特にFIRE後は、生活コストや体力、家族の状況などに応じて、業務を調整したくなるケースも増えてきます。
具体例:私の出口戦略
| 状況 | 法人の扱い | 個人事業主の扱い | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 維持 | Web制作+賃貸で継続 | 土地の賃貸を継続 | 現状のまま安定運用 |
| 縮小 | 法人は休眠 or 廃業 | 個人事業主のみで継続 | 申告・会計の手間を減らす |
| 終了 | 双方を整理 | すべて収益のない状態 | 投資や年金中心の生活へ |
このように、法人も個人も「完全に辞めなくてもいい」、「選べる」という柔軟性が、将来の不安を和らげてくれます。
特にマイクロ法人は維持コストが低く、赤字でなければ休眠や解散もしやすいため、FIRE後の変化にも柔軟に対応可能です。
個人事業主は廃業届だけで完了するため、再開も容易で、選択の自由度が高いのも魅力です。
会社設立から運用までの全体像は、こちらの記事でまとめています。
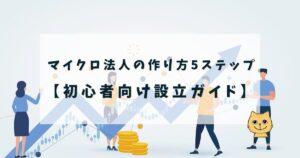
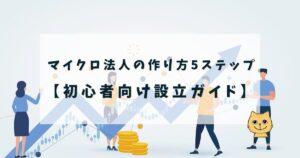
投資と連携することで資産形成が加速する


マイクロ法人と個人事業主の“二刀流”によって、両方の立場で投資ができるのは非常に強力なメリットです。
その結果、資産形成のスピードが2倍になります。
法人では「一般口座(申告分離課税)」による運用が基本になりますが、法人名義の証券口座を開設することで、利益の繰り延べや節税に活用できます。
一方、個人側では新NISA制度をフル活用することで、非課税の恩恵を最大限に受けることが可能です。
具体例:私の投資の使い分け
| 立場 | 利用サービス | 投資対象と戦略 |
|---|---|---|
| 法人名義 | 住信SBIネット銀行 → SBI証券(法人) | S&P500中心にインデックス運用。節税+損益通算の管理を徹底 |
| 個人名義 | 夫婦で新NISAを年初一括投資 | オルカン&S&P500で非課税枠をフル活用 |
同じインデックス投資であっても、「税制の強み」を使い分けることで、最終的な資産の伸びに大きな差が生まれます。
なお、新NISAは「やらなきゃ損」と言えるほどの制度ですので、個人側では最優先での活用を推奨します。
新NISA戦略の詳細はこちらの記事で解説しています。


最強のFIRE戦略を実現する“二刀流”のまとめ


マイクロ法人と個人事業主を“二刀流”で運用することで、節税・社会保険料対策・投資の最適化をすべて両立でき、FIRE戦略の完成度が飛躍的に高まります。
これは、私が実践している“サイドFIRE”の中核でもあり、「無理なく続けられる仕組み」として非常に効果的です。
なぜなら、法人の信用力・社会保険制度・会計の柔軟性を活かしながら、個人ではNISAやライフスタイルに応じた柔軟な出口戦略を選べるからです。
一方を捨てるのではなく、「両方を活かす」戦略だからこそ得られる、7つの具体的メリットがこちら:
- 社会保険料の最適化:国保→社保へ移行して負担を抑制
- 所得分散による節税:法人+個人で手取り最大化
- 経費計上の幅拡大:二重計上せずに柔軟に振り分け
- 会計・申告の簡素化:クラウドツールで効率化
- 法人の信用:在宅でも法人契約で信頼性UP
- 柔軟な出口戦略:どちらか一方のみ残すことも可能
- 投資との連携:法人+個人でインデックス投資を加速
このように、マイクロ法人と個人事業主の“二刀流”は、FIRE後も安心して資産を守りながら生活を続けられる強力な土台となります。
特に「サイドFIRE」や「在宅FIRE」を目指す方にとって、再現性の高い選択肢としておすすめです。
次のステップとして、マイクロ法人の設立方法や、個人事業主とのバランス調整についてもあわせてご確認ください。