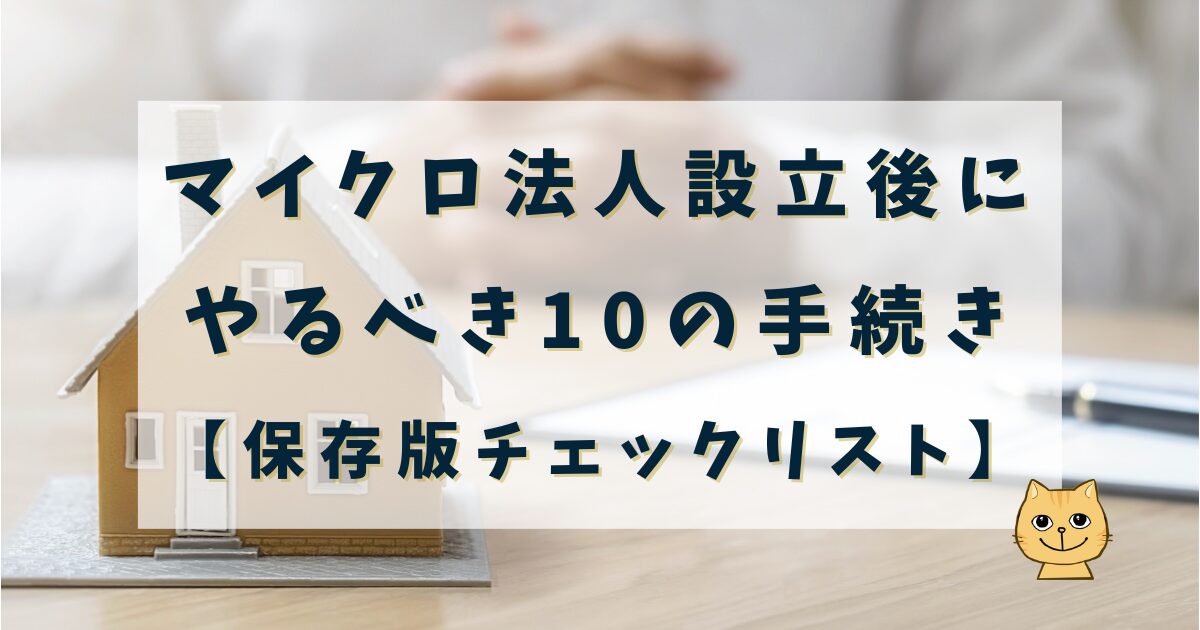マイクロ法人を設立したはいいけれど、このあと何をすればいいの?
と不安になる方は少なくありません。
登記が完了しても、それは“スタート地点に立っただけ”。
実はその後にやるべき手続きが数多くあります。
特に、銀行口座の開設、税務署への届出、社会保険の準備など、初動で間違えるとあとで大きな手間や損失につながるものも…。
でも安心してください。
この記事では、設立直後に必要な10の実務手続きを、チェックリスト形式で網羅的にまとめました。
私自身もマイクロ法人を運営しながら、これらの手続きを実践済み。
実体験に基づいた順番と優先度で、初心者にもわかりやすく整理しています。
この記事を参考にすれば、迷うことなく次の一手を進められ、スムーズな法人運営の土台を築けます。
それでは早速、チェックリストの1つ目から確認していきましょう!
法人口座の開設【金融機関の選び方と必要書類】


会社設立後、最優先でやるべき手続きの一つが銀行口座の開設です。
売上や経費の管理を個人口座と分けることで、経理や税務処理もスムーズになります。
金融機関の選び方
法人用の銀行口座には、大きく分けて次の2種類があります。
| 金融機関 | 特徴 |
|---|---|
| メガバンク系 | 審査が厳しい/店舗対応が多い/信頼性が高い |
| ネット銀行系 | オンライン完結/低コスト/審査の柔軟性が比較的高い |
特にマイクロ法人や在宅起業を前提とした場合、ネット銀行の利便性とコストパフォーマンスは大きな魅力です。
おすすめ:住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行の法人専用口座は、マイクロ法人との相性が非常に良いです。
- オンライン申込で手続き完結
- 無料の振込枠あり
- 低コストで使いやすいインターフェース
書類の整え方・審査に落ちないための注意点も詳しく解説しています。


口座開設に必要な書類
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 印鑑証明書(法人)
- 代表者の本人確認書類(運転免許証など)
- 法人実印
- 会社の定款
- 開業届または事業計画書(補足資料として求められることも)
開業初期でも口座開設しやすい銀行を選び、早めに準備を進めましょう。
税務署への届出【設立届出書・青色申告の申請】


マイクロ法人を設立したら、税務署へ提出する3つの書類があります。
期限が決まっているため、必ずチェックしましょう。
| 書類名 | 提出期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立日から2ヶ月以内 | 会社設立を報告する基本の届出 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立日から3ヶ月以内 or 第1期の期末の早い方 | 節税に有利な「青色申告」を選ぶために必要 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開業から1ヶ月以内 | 役員報酬を支払う場合に必要 |
書類作成は「マネーフォワード 会社設立」で一括管理!
マイクロ法人の税務関連書類は、「マネーフォワード 会社設立」を使えば、画面の案内に従うだけで自動作成・印刷が可能です。
手書き不要・無料で利用でき、提出先の案内も付いているため、初心者でも安心です。
書類作成・管理はこれで安心です。
税務署への届出のタイミングや手続きの流れを年間スケジュールで確認できます。
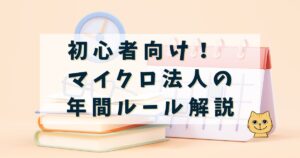
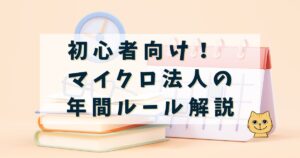
都道府県税事務所・市区町村への届出


税務署とは別に、都道府県税事務所と市区町村にも設立届を提出する必要があります。
提出しないと、法人住民税や法人事業税の通知が来ない場合もあります。
提出先と書類は自治体ごとに異なる
- 都道府県税事務所 → 「法人設立届出書」
- 市区町村(役所) → 「法人設立届出書」または「事業開始申告書」など
提出期限:設立から1ヶ月以内が目安(自治体により異なる)
提出方法は主に以下の3つ
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 郵送 | 手間が少ない | 書留などで控え返送希望を記載 |
| 窓口持参 | 担当者に確認できて安心 | 平日のみ、自治体ごとの受付時間に注意 |
| 電子申請(eLTAX対応) | オンラインで完結 | 一部対応していない自治体もあり |
提出先の確認方法
各自治体のWebサイトで「法人設立届出書」と検索すれば、該当のPDFや記入例が見つかります。
迷ったら、電話確認が最も確実です。
「都道府県」「市区町村」それぞれに提出する必要があるのは、忘れやすい落とし穴です。
都内であれば、東京都主税局+市区町村、などセットで考えておきましょう。
地方税の手続きタイミングも一覧でチェックできます。
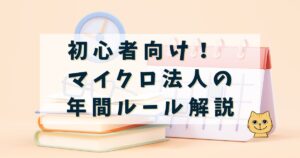
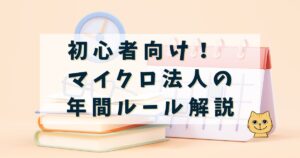
年金事務所への届け出【新規適用届・被保険者資格取得届】


法人を設立すると、たとえ役員1人だけのマイクロ法人でも、健康保険と厚生年金への加入が義務となります。
そのため、所轄の日本年金機構(年金事務所)に以下の書類を提出し、社会保険の適用事業所として登録しなければなりません。
提出が必要な書類一覧
| 書類名 | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規適用届 | 管轄の年金事務所 | 事業所として健康保険・厚生年金を適用 |
| 被保険者資格取得届 | 同上 | 役員や従業員が社会保険に加入するための書類 |
| 登記簿謄本・定款の写しなど | 同上 | 補足資料として必要になることが多い |
提出期限
登記設立日から5日以内(遅れても受理されますが、なるべく早く提出を)
提出のポイント
- 管轄年金事務所は、日本年金機構のサイトで調べられます。
- 書類の記載ミスや添付漏れがあると、再提出になることも。
- 役員報酬額をどう設定するかで、保険料が大きく変動します。
社会保険の加入は、今後の「信用力」や「税務調査」でも見られる重要ポイントです。
将来的に報酬調整や保険料削減を考えるなら、マイクロ法人×個人事業の併用戦略も選択肢です。
社会保険の加入義務や節約術を詳しく解説しています。


社会保険の年間スケジュールも紹介しています。
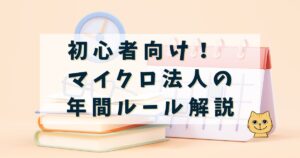
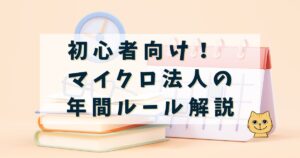
労働基準監督署・ハローワークへの届け出【従業員を雇う場合】


マイクロ法人では、代表1名のみでスタートするケースが多いですが、今後パートやアルバイトを雇う場合には、労働基準法・雇用保険法上の届け出が必要です。
提出が必要な主な書類(従業員を雇用する場合)
| 書類名 | 提出先 | 内容・目的 |
|---|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 労災保険の適用手続き(雇用日から10日以内) |
| 雇用保険 適用事業所設置届 | ハローワーク | 雇用保険の適用手続き(雇用日から10日以内) |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | ハローワーク | 従業員1人ずつに提出(雇用日から10日以内) |
対象となる「従業員」の範囲とは?
- 雇用保険の対象:週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある従業員
- 労災保険の対象:すべての従業員(時間・日数を問わない)
代表1人の法人では不要なことが多い
- 法人代表(社長)だけで運営している場合、これらの届け出は不要です。
- ただし、配偶者や親族を手伝わせる場合でも、名目上「従業員」扱いになる可能性あり。
注意しましょう。
労働基準監督署・ハローワークの手続きは、電子申請できないケースが多く、原則郵送か持参です。
従業員を雇う前に、届け出先や必要書類をリスト化しておきましょう。
給与処理の手間をクラウドで効率化する方法を紹介しています。


法人住民税・法人事業税の納付準備【納付書やeLTAX】


マイクロ法人を設立すると、税務申告前でも支払いが必要な税金があります。
特に、「法人住民税」と「法人事業税」の納付準備は早めに行うべきです。
主な税金の種類と特徴
| 税金の種類 | 納税先 | 課税内容 | 納付時期 |
|---|---|---|---|
| 法人住民税(均等割) | 都道府県・市区町村 | 所得に関係なく発生 | 毎年(原則)決算後2ヶ月以内、予定納税あり |
| 法人事業税 | 都道府県 | 所得に応じて発生 | 所得が出た場合のみ課税 |
※赤字でも法人住民税(最低7万円程度)はかかるため注意。
eLTAXでのオンライン手続きを活用しよう
紙の納付書を使った納付も可能ですが、以下の理由からeLTAX(地方税ポータルシステム)の利用が推奨されます:
- 電子申告・納付がまとめて可能
- 利用開始には「利用者ID登録」が必要
- 「マネーフォワード クラウド会計」とも連携可能
eLTAXの登録は、法人番号取得後すぐにできます。
決算期を迎える前に準備しておくと、申告・納付がスムーズに進みます。
eLTAXと連携できるクラウド会計で納税準備を効率化!


会計ソフトの導入・設定【クラウド会計の初期設定】


マイクロ法人では、設立日からのすべてのお金の動きが記帳対象になります。
「後でまとめてやればいい」はNGで、初期設定をサボると決算前に大きな手間になります。
おすすめは「マネーフォワード クラウド会計」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入タイミング | 法人口座・クレカが揃ったらすぐ |
| おすすめツール | マネーフォワード クラウド会計 |
| 連携できるもの | 銀行口座・クレジットカード・給与計算 |
| 主なメリット | 自動仕訳・電子帳簿保存対応・税理士と共有しやすい |
導入・初期設定の流れ
- マネーフォワード クラウド会計のアカウント作成(設立プランとの連携OK)
- 法人口座・法人カードを登録
- 勘定科目や消費税設定の初期調整
- 月次の記帳と証憑(領収書等)の管理ルール整備
会計ソフトは、最初から自動化・連携を前提に構築するとラクです。
確定申告や消費税対応も考え、早めに体制を整えましょう!
初心者でも導入しやすく、税理士と共有できる安心設計。
会計ソフト選びの背景とおすすめ活用法を解説しています。


請求書や領収書のフォーマット作成
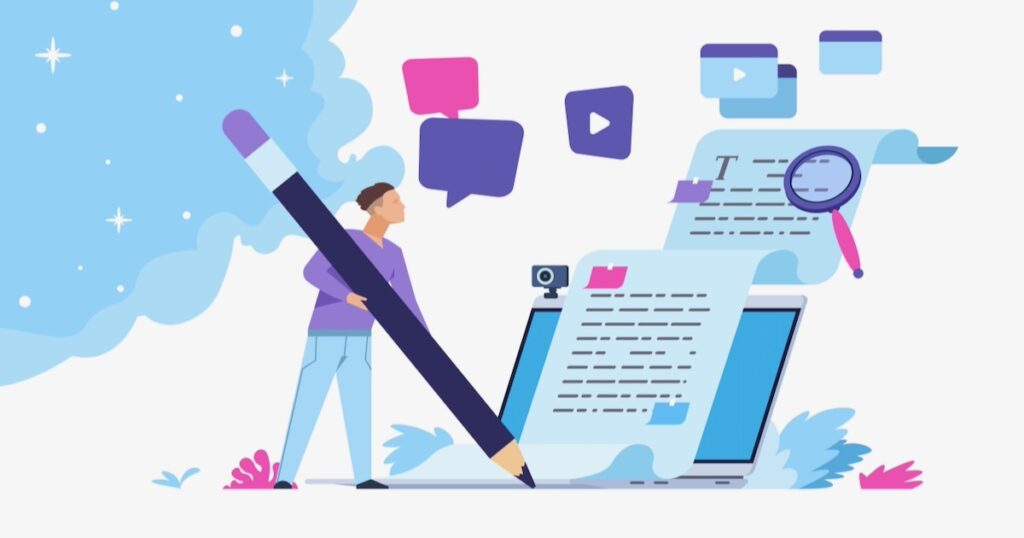

取引金額の大小にかかわらず、法人間の取引では証憑(しょうひょう)をきちんと残すことが求められます。
特にインボイス制度の開始以降、適格請求書の形式を満たす必要がある場面もあります。
請求書・領収書の要件まとめ
| 種類 | 必須項目 | 補足 |
|---|---|---|
| 請求書 | 発行日・請求先・発行元・金額・明細・振込先・登録番号 | インボイス登録番号がある場合は記載 |
| 領収書 | 発行日・受領金額・支払者名・発行者情報・但し書き | 収入印紙の有無に注意(5万円以上) |
無料テンプレートで作成する or 会計ソフト連携
- ExcelやGoogleスプレッドシートで自作(無料テンプレあり)
- 会計ソフト(マネーフォワード クラウド会計)で発行・管理
┗ 請求書の送付、入金状況、仕訳処理まで一元管理できます
インボイス対応は「登録の有無」で変わる
インボイス発行事業者であれば、登録番号の記載が必須。
登録しない場合でも、今後の取引先によっては求められるケースもあるため、事前の判断が重要です。
書類フォーマットは、「テンプレを使ってすぐ出せる状態」にしておくことが実務効率UPのカギです。
特に請求書の形式不備で信頼を失うことがないよう、正しい様式+見やすいデザインを意識しましょう!
請求書管理もラクになる「クラウド会計の強み」を紹介しています。


請求書の作成 → メール送信 → 入金消込 → 会計連携まで一括管理。
社会保険・労働保険の加入要否と対応


社会保険・労働保険は、加入が“義務”かどうかをまず確認!
マイクロ法人を設立したら、役員1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生します。
一方で、労働保険(労災保険・雇用保険)は“従業員を雇ったときのみ”対応が必要になります。
加入要否と対応フロー
| 保険の種類 | 加入義務の有無 | 対象者 | 届出先 | 申請書類の例 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金(社会保険) | 原則あり(法人は強制) | 代表者(役員) | 年金事務所 | 新規適用届、被保険者資格取得届 |
| 労災保険(労働保険) | 労働者を雇った場合のみ | 従業員 | 労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 など |
| 雇用保険 | 労働者を雇った場合のみ | 従業員 | ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 など |
よくあるマイクロ法人の対応例
- 役員1名(自分のみ)で社会保険に加入
┗ 原則義務。 - 労働保険は未加入でOK(従業員ゼロの場合)
┗ 今後雇用予定がある場合は事前に確認しておくとスムーズです
社会保険の加入判断は、設立直後の「役員報酬額」や「家族の扶養関係」にも影響します。
社会保険の「加入タイミング」や、期首・役員報酬の兼ね合いも紹介しています。
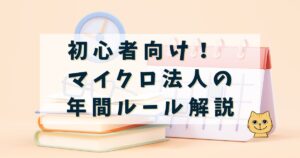
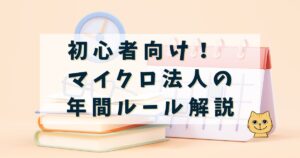
名刺・印鑑・法人用クレジットカードの整備【信用力アップ】
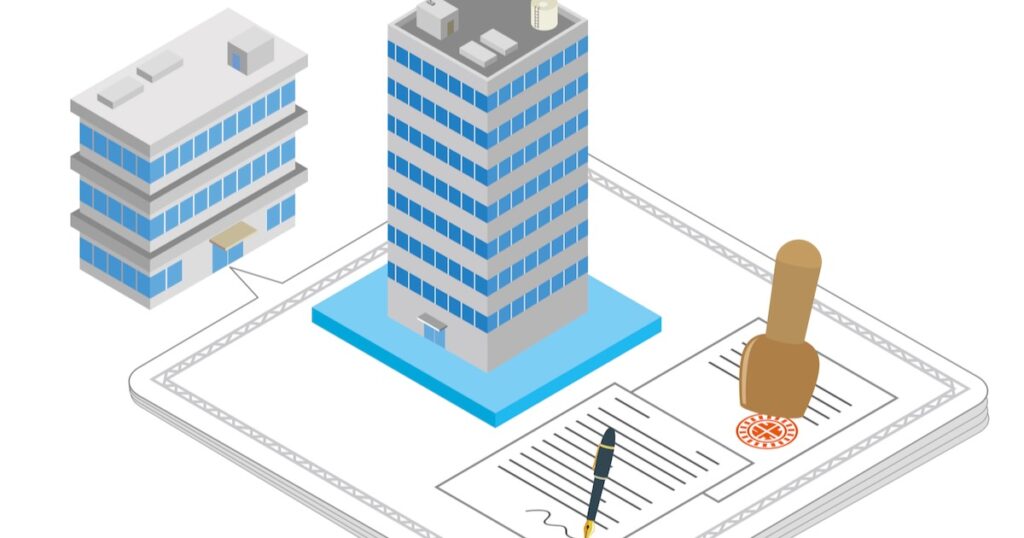

事務的な準備だけでなく、「法人の体裁づくり」も重要です!
マイクロ法人といえど、対外的な信用力や手続きの円滑化を考えると、「体裁の整備」は欠かせません。
名刺や会社印、法人用クレジットカードなど、“見た目”と“実務”の両面から整えておくことが大切です。
必須アイテムとその役割一覧
| 項目 | 必要性の理由 | 注意点・おすすめサービス |
|---|---|---|
| 法人名刺 | 顧客・関係者への信頼感アップ | 屋号だけでなく「会社名」「役職」も明記 |
| 会社印(実印・銀行印など) | 登記・契約・銀行口座手続きに必要 | 3点セットでの購入がおすすめ |
| 法人用クレジットカード | 経費の分離・仕訳効率化・信用情報の構築 | 審査基準が個人と異なるため早めの準備が安心 |
おすすめの整備順
- 会社印(登記後すぐ)
┗ 銀行口座や契約書類など、すぐに必要になる場面が多いため。 - 法人名刺(名乗る前に)
┗ 取引先や業者に会社を紹介する準備として、早期に用意。 - 法人クレカ(会計効率と信用のため)
┗ 経費の見える化や仕訳効率、信頼にもつながる。
法人クレジットカードの審査は「登記簿謄本」「決算書類」が求められることも。
早めに作成・取得しておくことで、資金繰り・会計管理がグッと楽になります!
銀行印・法人名義の重要性についても紹介しています。


まとめ|設立後の手続きで信頼ある法人運営を


マイクロ法人を立ち上げたあと、「やることが多すぎて混乱しそう…」という方も多いはず。
でも、今回ご紹介した10のチェックリストをひとつずつクリアしていけば、信頼性のある法人運営の第一歩を着実に踏み出せます。
チェックリスト再確認(10の手続き)
- 銀行口座の開設
- 税務署への届出(設立届・青色申告など)
- 都道府県税事務所・市区町村への届出
- 年金事務所への届出(社会保険の適用)
- 労働基準監督署・ハローワークへの届出
- 法人税・住民税・事業税の納付準備
- 会計ソフトの導入と初期設定
- 請求書・領収書のフォーマット整備
- 社会保険・労働保険の加入要否確認
- 名刺・印鑑・法人クレカの整備
ポイント整理
- 提出先が多いので、スケジュールを立てて進めるとスムーズです。
- 社会保険の加入有無や役員報酬の設定は、法人運営の方向性と連動するため戦略的に決めましょう。
- 口座・会計・クレカの整備は実務効率と法人信用を高める上で重要です。
次に読むべきおすすめ記事
そもそもどうやって法人を作るのかを手順付きで解説しています。
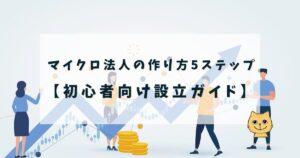
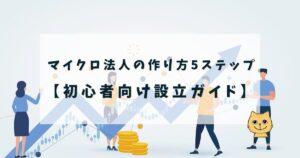
節税と保険料の最適化を狙うなら「併用」がカギです。


マイクロ法人設立はゴールではなく、スタートです。
実務を一つひとつ丁寧に整えることで、「小さくても強い法人」が育っていきます。
一緒に着実な一歩を踏み出していきましょう!