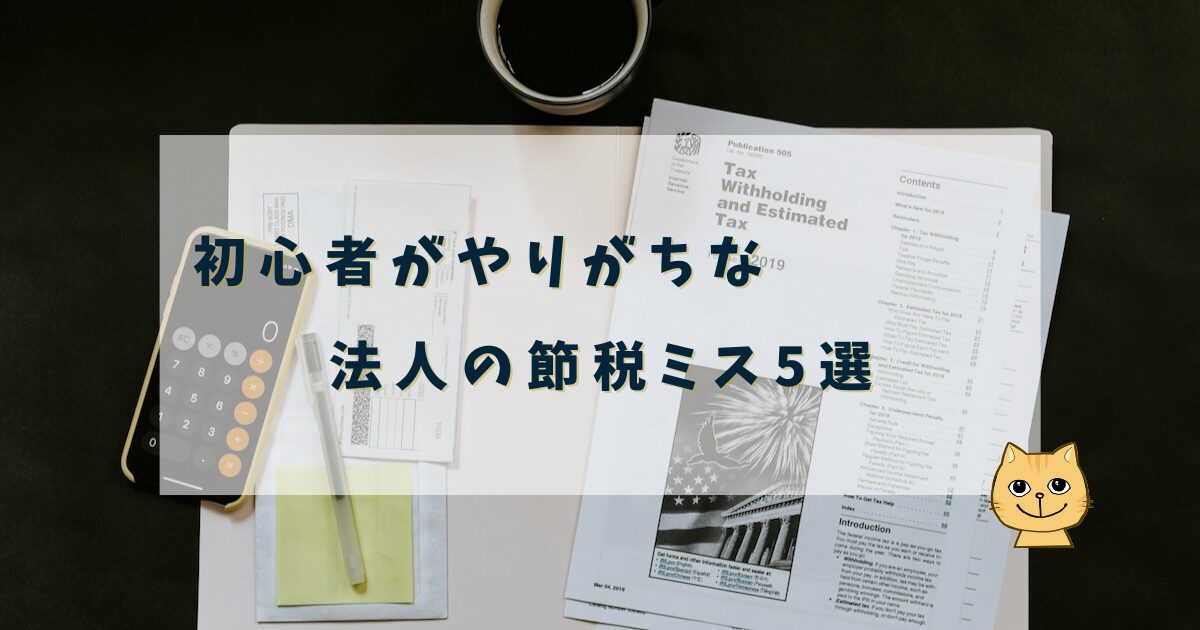節税のためにマイクロ法人を設立したものの、あれ?思ったほど節税できていない…
あとから税理士に指摘されて修正する羽目に…
マイクロ法人を立ち上げて「節税になる」と聞いて始めたものの、実は損をしている人も少なくありません。
この記事では、初心者がやりがちな法人の節税ミスを5つ取り上げ、どうすればそれを防げるかを解説します。
私自身もいくつかのミスを経験しながら、改善してきました。
この記事が、あなたの「無駄な出費を防ぐ」参考になれば幸いです。
ミス①:報酬設定が高すぎて社会保険料が割に合わない
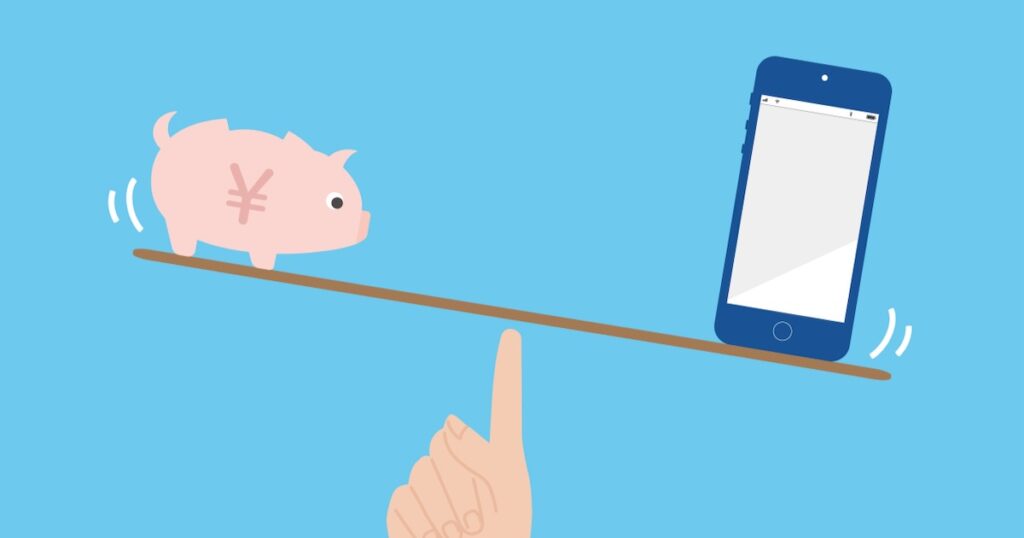

法人代表者の報酬は、多すぎても少なすぎても損をします。
特に初心者がやりがちなのが、会社員時代の感覚のまま高めに設定してしまい、所得税・住民税・社会保険料が跳ね上がるパターンです。
社会保険料のコントロールを意識した設計が重要です。
「マイクロ法人の節税で見落としがちな5つの方法」では、役員報酬の最適化について詳しく紹介しています。
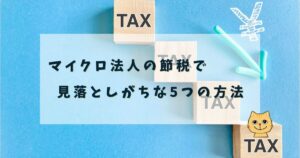
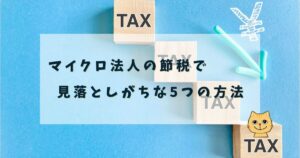
報酬額のシミュレーションや社会保険の試算には、税理士との相談や会計ツールの活用が欠かせません。
ミス②:経費にできるものを見落としている


マイクロ法人の初心者に多いのが、「本来なら経費にできる支出」を見逃してしまうことです。
たとえば、自宅の一部を仕事場として使っている場合、その光熱費や通信費の一部は経費として計上できます。
また、法人で使っているパソコンやモニター、オフィスチェアなども、「業務利用が明確なもの」は法人経費にできるのが基本です。
これを見落としてしまうと、本来節税できた金額をムダに納税してしまう結果に…。
実例とポイント
たとえば私は、自宅での法人業務にあたり「オフィスチェア」や「PC周辺機器」を法人で購入・経費計上しました。
これにより、数万円単位の節税が実現しています。
法人向けにおすすめのオフィスチェアはこちらで紹介しています。


Amazonや楽天市場での法人購入にも対応しているので、経費計上しやすい環境が整っています。
節税は「正しく使うこと」で初めて効果が出ます。
まずは、法人で使っているモノ・サービスが経費にならないかを必ずチェックしてみましょう。
ミス③:売上ゼロでも法人住民税はかかることを知らない


マイクロ法人は「売上がゼロでも税金がかかる」ことを見落としている方が多いです。
特に見落としがちなのが「法人住民税の均等割」。
これは利益の有無にかかわらず、法人が存在するだけで毎年かかる最低税額で、多くの自治体では年間約7万円ほど発生します。
この均等割を知らずに、1年目から赤字・売上ゼロで運営を始めてしまうと、「えっ、なんで赤字なのに税金が?」と驚くことになります。
対策と心構え
マイクロ法人を作る場合は、「最低でも年間7万円程度の法人維持コストがある」と最初から見込んでおく必要があります。
これは“会社を持つことの基本コスト”と考えましょう。
また、経理処理を通じて法人の状態を常に把握しておくことも大切です。
会計の基本を押さえておくと、毎年の税額の見通しも立てやすくなります。
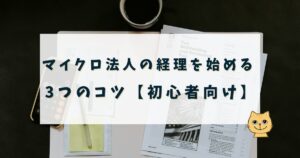
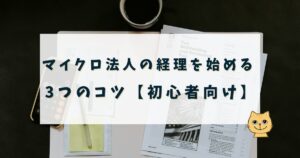
会計処理を効率化するには「マネーフォワード クラウド会計」がおすすめです。
法人の会計・決算・確定申告まで対応できます。
「売上がない=税金もゼロ」ではありません。
マイクロ法人には最低限の維持コストがかかることを理解し、適切な会計管理で無駄なミスを防ぎましょう。
ミス④:事業年度の設定を適当に決めている
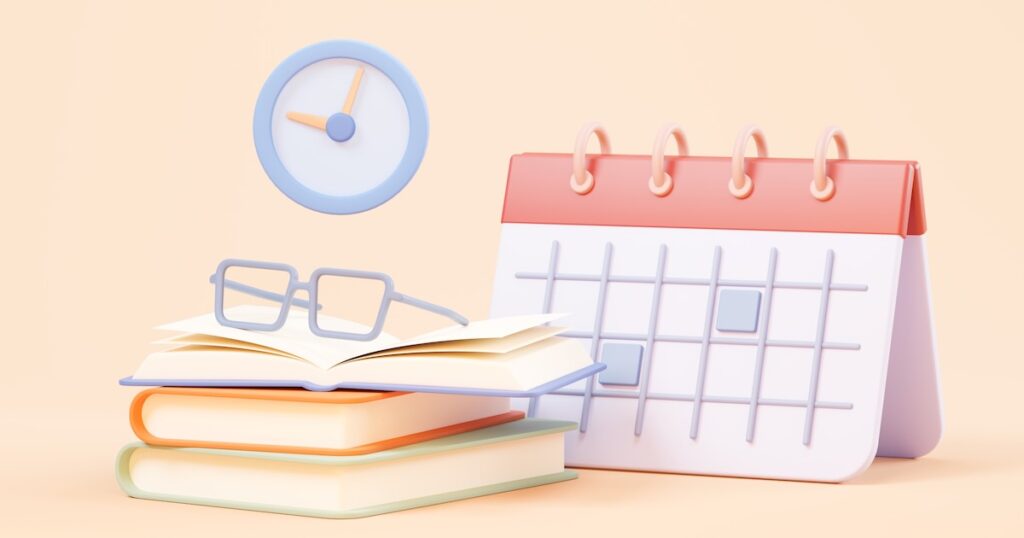

マイクロ法人を設立する際、「事業年度」をなんとなくで決めてしまうのは大きなミスです。
事業年度は会社設立時に「自由に設定できる」ため、つい「設立月=期首」で登録してしまいがちですが、これは節税のチャンスを失う可能性があります。
節税戦略と事業年度はセットで考える
たとえば「役員報酬の設定月」や「売上計上のタイミング」「個人事業の収入とのバランス」によって、事業年度の区切りを工夫することで、税金や社会保険料の負担を抑えることができるケースがあります。
設立のタイミングから逆算して事業年度を設計することで、利益が出にくい最初の期の法人住民税も抑えやすくなります。
設立時に見落としがちなポイントをまとめています。事業年度の設定はステップ3で解説。


「マネーフォワード クラウド会社設立」では、設立書類の作成時に事業年度の入力もガイド付きでスムーズに進められます。
実際に私もこのサービスを使って設立しました。
マイクロ法人の「事業年度」は後から簡単には変えられません。
設立時にしっかりと計画を立てて設定することで、節税にもつながる大切なポイントです。
ミス⑤:節税目的で外注費を使いすぎる


「利益を圧縮するために外注費を使えばいい」と考えるのは危険です。
確かに、マイクロ法人では「赤字=税金がかからない」ため、外注費を使って節税するという発想は一見理にかなっています。
しかし、これは短期的な視点にすぎません。
必要以上の支出は逆に損をする
税金が減っても、それ以上にキャッシュアウト(手元資金の減少)が大きければ意味がありません。
さらに、不自然な支出が続けば税務署からのチェック対象になるリスクもあります。
マイクロ法人の節税は、「節税=支出」ではなく、「最小限の支出で最大限の効果」を意識した設計が重要です。
外注費に頼らない節税テクニックも紹介しています。
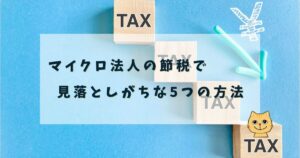
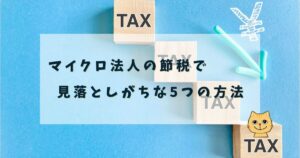
「マネーフォワード クラウド会計」を使えば、支出の項目やバランスも視覚的に把握でき、無駄な出費の見直しにも効果的です。
私も月次でレポートを確認しています。
節税のための支出は「目的が明確」で「効果がある」ものだけに絞るべきです。
安易な外注費の多用は、資金繰りや信用リスクに繋がる可能性があるので注意しましょう。
まとめ:節税は「合法かつ効果的」が基本


初心者のうちは「節税=支出を増やすこと」と誤解しがちですが、本当に重要なのは「お金を残す設計」です。
本記事で紹介したようなミスを避けるだけで、年間のキャッシュフローに大きな差が出てきます。
また、節税は単発のテクニックではなく、中長期の法人運営における“戦略”です。
さらに実践的なテクニックを知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
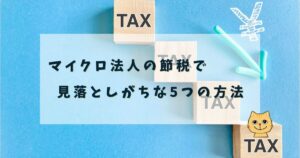
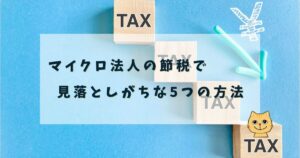
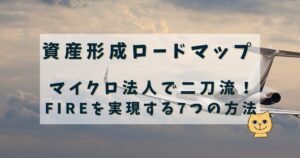
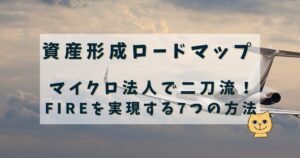
よくある質問(Q&A)


Q1. 節税って赤字にすればいいってことじゃないの?
A. 一時的な赤字は問題ありませんが、毎年続くと税務署に目をつけられます。
また、赤字を続けると社会的信用(融資や口座開設など)も落ちるため、利益の調整はあくまで“計画的に”行うことが大切です。
Q2. 節税の相談は税理士にすべき?
A. 節税スキームの構築やリスク回避には、専門家の力が役立ちます。
特にマイクロ法人のような小規模運営では、クラウド会計×税理士の組み合わせが最も合理的です。
「マネーフォワード クラウド会計」は、仕訳や経費計上も簡単。
税理士との連携もスムーズになります。
Q3. 外注費を使って節税しても大丈夫?
A. 目的が明確で、業務の実態がある場合に限られます。
形式だけの外注費や、相場を超えた支出は「経費」として認められない可能性も。
“実態のある支出かどうか”を常に意識しましょう。